

① はじめに、研究対象である、ヒカゲノカズラ科の植物を採集、収集します。
② 植物を3〜4 cmくらいの長さにハサミできります。
③ メタノールとともに、ミキサーにかけます。
ウィーーーーン!!!!
④ 三角フラスコに移し、しばし放置。
⑤ ろ過し、
⑥ ろ液をエバポで濃縮し、
⑦ メタノールエキスを作ります。
エキスといったら、ドロッとしたイメージがあるかもしれませんが、
採取した植物の状態によって、さまざまです。
⑧ 植物の成分全体を見るのであれば、そのエキスをそのままカラムにかければよいですが、本研究では、アルカロイドの分離を目的としているので、アルカロイド分配という液々分配を行い、効率よくアルカロイド成分を分離します。
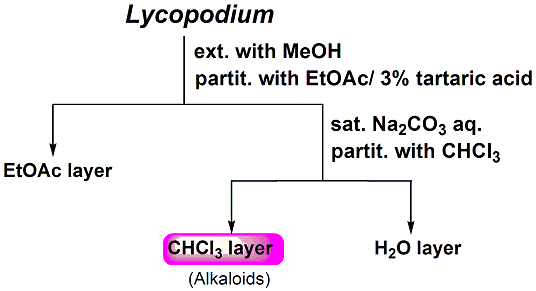
例として、上の図は当研究室でよくやられる操作を示したものです。
(Ⅰ) 植物をメタノールで抽出して得られたメタノールエキスを、酢酸エチルと酒石酸水溶液で分配
上の黒い部分(酢酸エチル層)と下の茶色い部分(水層)にわかれる。
(Ⅱ) 得られた水層に、炭酸ナトリウム水溶液を加えて塩基性にした後、クロロホルムと分配
炭酸ナトリウム水溶液を加えると、二酸化炭素が発生。
スパーテルの先に液体をちょこっとつけて、
pH試験紙につける。
pH試験紙は、ほんのちょこっと切ったもので十分。
およそpH9〜10の塩基性になりました。
クロロホルムを加えて、分配をすると、
上の茶色い部分(水層)と下のうす黄色い部分(クロロホルム層)にわかれる。
(Ⅲ) クロロホルム層にアルカロイドが移行し、効率よくアルカロイドが得られる
⑨ 得られたクロロホルム層を濃縮後、カラムにかけます。
⑩ 分離をおこなった画分にTLCを行い、ドラーゲンドルフ試薬に対する呈色具合を見ます。
(橙色になったところに、アルカロイドがいるのがわかります。)
⑪ 単離が成功しているようだったら、NMRなどの測定を行い、構造解析。失敗の場合は、さらにカラムなどで分離をします。